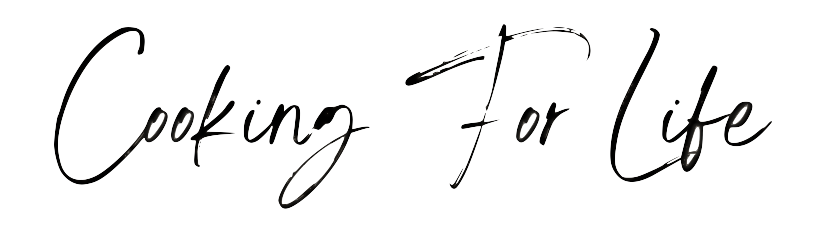反応の世界を脱して、道を歩き始めたことについて

自分で「私は成長しました」などというのは、やや客観性に欠けた野暮な自惚れなのかもしれない。
それでも、今お腹に力を込めて、空気にはっきり響く声で言いたい。
「善き表現者として、スタートラインに立つことが出来ました」と。
全ての細胞が書き換わったような感覚であり、かといって無碍に高揚もしていない、中庸。
いい状態だな、と自分でも思える。

このブログは「あなたの心とお腹を満たす」をコンセプトに「インターネットで課題を解決したい、悩みを解決したい、という人にとって役立つもの」を目指して始めた。
だから、こういういわば「自分語り」のコンテンツを主観で書いてみても、「資産」としては何の足しにもならない、技術的なノウハウの観点では。
本来は「見出し」や「目次」をつけて、「この記事は読み手にとって何の役に立つのか?何の足しになるのか?」をわかりやすくするのが定石だ。そしていつも心がけている。
わかっていながら、こうして「あなたの足しになるかどうか考えていない」記事を書いている。
それだけ、「料理研究家」として、「ダイちゃん」としてブログを書いている、私自身が、魂本体レベルで「よー頑張ったなぁ」「よく乗り越えたなぁ」と思えた日だったからだ(執筆は公開前日の6月25日)。

上京してはや16年が経過した。大学(大阪)で故郷を出た年数を考えれば、すでに人生の半分以上を「大都市」といわれる場所で過ごしている。
仄暗い青春時代を息を止めて過ごした自分のような人間にとっては、そこからはただただ、コンプレックスを解消し、承認とプライドを取り戻すための流浪の旅だった。
それは年齢による成熟や、社会的な承認などではおさまることはなく、もはや幻でしか無い「理想」や「敵」との戦いだった。
自意識ばかりが過剰になり、自らの欠落を反動に他者を傷つけ続けた。
天性でもらって生まれた「人柄」という特許に甘えて、多くの人の徳を栄養に、生きながらえてきた人生だった。
 それでもいろいろな帳尻はあうようになっていて、欠落と利己だけをガソリンに走ってきた車は噴煙を上げ、いつしか1センチも前に進めなくなった。そこには煙を上げる大きな車体と、幾ばくの別れと、絶望だけが残った。
それでもいろいろな帳尻はあうようになっていて、欠落と利己だけをガソリンに走ってきた車は噴煙を上げ、いつしか1センチも前に進めなくなった。そこには煙を上げる大きな車体と、幾ばくの別れと、絶望だけが残った。
おおよそ4年くらい前のことだ。あの時の辛さを思えば大抵のことは乗り越えられると思うほど、壮絶に苦しんだ日々だった。起き上がれないベッドには自分の跡が残るほどに見え、結わえたロープをかばんに入れて別の世界に逃避する場所を探して歩いたこともあった。
そこから生き戻るには様々な巡り合わせ、人の救い、複雑な要素が絡み合い活字にとても出来ないのだが、確かに掴んだ蜘蛛の糸は、それまでがむしゃらに生きてきた中でつながった人のご縁と、「料理」との出会いだった。
生き残った。けれど、人間簡単に変わることはなく、「追い詰められこの世を去りたいという気持ち」への耐性は頑強になったが、「欠落を盾にした承認欲求」は潰えることはなかった。修業の日々は続いた。

時間の問題だった「爆発」そして「限界」は19年末に訪れる。
見たことあるようなパターンの失敗、自分は間違っていないという倒錯、自己嫌悪にまみれた。
旅先の京都で酒を浴びてはごまかした。
「なんでオレばっかり・・・」
脳をアルコールで浸しても、意識も心理も解釈も、変わることはない。
そんな「挫折」が、人生を変える出会いを引き寄せた。
「傷を負ってきたプロフェッショナルであり、師事すべきメンタルトレーナー」との出会いだった。

捻じ曲がった本質や欠落を、容赦なく修正していく日々が始まった。
そう書けば簡易に映るが、それは壮絶な試練の日々だった。
欠落に屑が溜まり、膿んで爛れた心は腐臭を放っていた。だが師は言った。
「私は何があっても逃げません」
逃げようとしていたのはむしろ僕の方だった。立ち向かう覚悟を決めた。
欠落から逃避せず、刮目し、対峙すると決めた。家にこもるべき時期が来たことは、むしろ幸いだった。
余計な自意識から離れ、ただ必死で毎日積み重ねた。
とにかくコツコツ、日々を生きる。
逃避せず、己と純粋に向き合い、承認をしていった。積み重ねた先に、今日があった。

日々を穏やかに生きている。夢はある、ささやかだが野望もある。
だが、「そうしなければならない」ことはひとつもない。
ただ、一日一日、ベストを尽くす。それだけを考えて、実践して、過ごしている。
大きな山を乗り越えたわけでも、巨大な敵を討伐したわけでもない。
ただ、自らの意識を変えて、世界の見方をかえたということ。
今日もまた一歩進む。そのことが、より善い言葉を、レシピを、知識を、何より愛を、ひとつでも世に放つための方法だと信じて。
遠回りの人生には、愛すべき出会いと、つながりと、喜びが満ちていた。
辛かったことが霞むくらいまぶしく、いまつながった環の上を歩いている。
もう大丈夫だ。さあ、はじめよう。そんな感覚で、自然な呼吸で、酸素をゆるやかに噛みしめながら、僕はまた走り出す。愛すべき人たちの顔が見える。