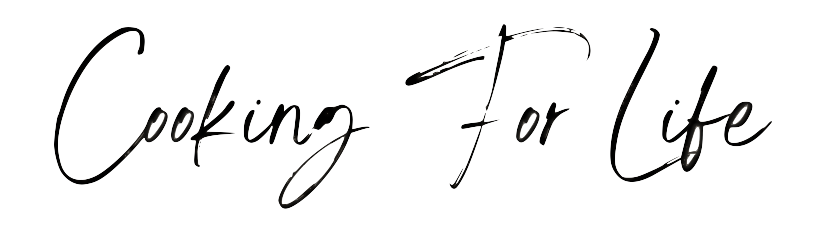保護中: 【料理写真】レシピランキング1位のプロが考える撮り方魅せ方とは?

この記事を書いている人 - WRITER -
料理研究家、料理で人生を楽しくする人。2017年、会社勤めの激務やストレスで体調を崩したことをきっかけに自炊経験0から料理を始める。食の改善で心身が回復し、料理にのめり込む。2019年より煮込み料理研究家(煮込みスト)として活動開始。2021年からは企業レシピ開発や料理の連載、地上波TV出演など活躍の幅を拡大。2022年2月、料理で人生を善くする人を増やしたい思いから、料理の楽しさを伝える活動「Cooking For Life(クッキングフォーライフ)」をスタートし、料理教室やケータリングを行う。美味い飯と酒マニア、音楽好き。料理と食への探究心は人百倍で、お客様から「メールや提案の文字から味がする」「美味いへの発想が無限」と言われるほど。2022年、初のFMラジオ出演に続き農林水産省からの熱烈なオファーで「NIPPON FOOD SHIFT」活動における「ニッポンの食NEXT座談会」に出演し日本経済新聞に掲載。大分県出身、都内在住。※「煮込みスト™」は料理研究家ダイちゃんの登録商標です。
この記事を書いている人 - WRITER -
料理研究家、料理で人生を楽しくする人。2017年、会社勤めの激務やストレスで体調を崩したことをきっかけに自炊経験0から料理を始める。食の改善で心身が回復し、料理にのめり込む。2019年より煮込み料理研究家(煮込みスト)として活動開始。2021年からは企業レシピ開発や料理の連載、地上波TV出演など活躍の幅を拡大。2022年2月、料理で人生を善くする人を増やしたい思いから、料理の楽しさを伝える活動「Cooking For Life(クッキングフォーライフ)」をスタートし、料理教室やケータリングを行う。美味い飯と酒マニア、音楽好き。料理と食への探究心は人百倍で、お客様から「メールや提案の文字から味がする」「美味いへの発想が無限」と言われるほど。2022年、初のFMラジオ出演に続き農林水産省からの熱烈なオファーで「NIPPON FOOD SHIFT」活動における「ニッポンの食NEXT座談会」に出演し日本経済新聞に掲載。大分県出身、都内在住。※「煮込みスト™」は料理研究家ダイちゃんの登録商標です。